銀行口座の相続でお困りの方へ
相続でお困りの方札幌 相続トップ>銀行口座の相続でお困りの方へ
- 出生から死亡までの戸籍といわれたがどのように集めてよいかわからない
- 銀行の窓口で相続手続きについて説明を聞いたが自分たちでできそうにない
- 地元に支店窓口がない銀行の通帳がでてきた
- そもそも今見つかった通帳ですべてなのか分からないので調べたい
- 平日は仕事で相続手続きをしている手間暇がない
- 相続手続きの代行をしてくれる専門家を探している
このようなことでお困りではないですか。たまき行政書士事務所では、北海道の相続手続に特化した事務所です。
銀行の相続手続きが複雑で面倒である又は手間暇がないという方は、当事務所でまとめて相続手続きを代行することが可能です。
銀行の相続手続についてお困りの際は、お気軽にお電話、メールもしくはラインにてお問い合わせください。
銀行(信用金庫、信用組合、JAバンク等)の相続手続きとは
 銀行の相続手続きとは、お亡くなりになった方(故人)の名義の普通預金や定期預金等を解約し、相続人様の口座へ移す作業のことをいいます。
銀行の相続手続きとは、お亡くなりになった方(故人)の名義の普通預金や定期預金等を解約し、相続人様の口座へ移す作業のことをいいます。
すでに亡くなっているお客様とはいえ、銀行としては大切に預かっていた顧客の預貯金を移転する(なくしてしまう)作業になりますので、間違いが許されません。
銀行の預貯金は、他の遺産と同じように、死亡した瞬間に共同相続人(戸籍上の相続人全員)の共有財産となりますので、相続人が一人でも関与しない状態で手続きを誤って行ってしまうと、その関与しなかった相続人から銀行等金融機関は、損害賠償請求をされる危険性があります。
また、銀行等金融機関は、共同相続人の一人あるいは他人がキャッシュカードなどで引き出せないような対策をとる必要があります。
このような理由から、銀行等の担当者の方は、相続人から死亡の事実を知った瞬間、故人の銀行口座を凍結し、銀行等の相続手続を厳格にする(正式な手続きを促す)ことで、故人の預貯金を保護しています。
非常に額が少ない普通預金を除いて(預金額が10万円から50万円くらいの預貯金の場合例外的に簡易的な相続手続きができることもあります。)、原則として、50万円を越えるような普通預金口座、定期預金口座は、正式な相続手続きをすることでない限り、解約できない仕組みとなっております。
もっとも、相続人様が悲しみの中このような銀行の仕組みを十分理解し、柔軟に対応することは、難しいといえます。
また、銀行によって案内方法が異なる場合も少なくなく、銀行の支店によっても、説明の慣れ不慣れがあり、銀行の窓口に行ったとしても解決しないことがあります。また、銀行のホームページなどで丁寧な解説をしているところはほとんどなく、来店前後にご自身で時間をかけて確認をすることも難しいです。
銀行の相続手続きの流れ
 銀行の相続手続きで必要なのは、
銀行の相続手続きで必要なのは、
- ① 相続人を確定するために必要な戸籍の収集作業
- ② 相続人全員の印鑑登録証明書の取得作業
- ③ 誰がいくら相続するのか相続人全員が協議をする
- ④ 銀行の手続き書類に全員の署名押印、もしくは、遺産分割協議書を用いての相続手続(相続税の申告が必要な相続案件については、必ず遺産分割協議書が必要となります。)
各手続きについて詳細な説明をすると、以下の通りとなります。
① 相続人を確定するために必要な戸籍の収集作業について
相続人を確定するためには、どの相続人のパターンでも共通しているのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
この被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める理由としては、子供がいるか死亡時点で妻がいるかを確認するためです。
銀行の相続の場合、出生時点の戸籍も必要となります。出生の戸籍とは、出生の事実が書いている戸籍では足りず、0歳時の時点で所属している戸籍です。
相続人のパターン(組み合わせ)は、大きく分けて3パターンあります。
細かく分類すると6パターンとなります。ここでは、大きく分けて3パターンの解説をします。
- 第1の相続人のパターンは、妻と子供のパターンです。
- 第2の相続人のパターンは、妻と尊属のパターンです。尊属とは、両親や祖父母のことです。
ただし、両親の段階で一人でも生きていれば、祖父母が関係することはありません。
その場合、妻と、生きている片親あるいは両親が相続人です。
- 第3の相続人のパターンは、妻と亡くなった方の兄弟や姉妹のパターンです。(いわゆる“兄弟姉妹相続”事案と呼びます。)
兄弟や姉妹が亡くなった方よりも先に死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子供(亡くなった方からみて甥や姪が相続人となります。)
どのパターンも妻が登場していますが、妻がいない場合には、
- 第1の相続人のパターンの場合には、亡くなった方からみて、子供のみが相続人
- 第2の相続人のパターンの場合には、亡くなった方からみて、尊属のみが相続人
- 第3の相続人のパターンの場合には、亡くなった方からみて、兄弟姉妹(又は、甥や姪)のみが相続人
となります。
相続人を確定するために必要な戸籍の収集作業について話を戻すと、
- 第1の相続人のパターンの場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と子供の現在の戸籍が必要になります。
- 第2の相続人のパターンの場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と両親の現在の戸籍が必要となります。ただし、両親が死亡して祖父母のいずれかが生きていれば、祖父母の現在の戸籍が必要となります。
- 第3の相続人のパターンの場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍と両親の出生から死亡の記載のある戸籍(祖父母の生年月日によっては、祖父母の死亡の記載がある戸籍も必要となります。)が必要となります。
両親の出生から死亡までの戸籍も必要であるということが盲点です。
さらに、被相続人の兄弟の現在の戸籍が必要となります。
ただし、先に兄弟姉妹が死亡していた場合には、先に死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍に加え、その子供(被相続人からみて甥や姪)の現在の戸籍が必要となります。
第3の相続人のパターンの場合、出生から死亡までの戸籍を揃えるのが、
- ⅰ. 被相続人
- ⅱ. 被相続人の両親
- ⅲ. (被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合)被相続人の兄弟姉妹
に及ぶので、戸籍の通数が合計で30通を超えることも稀ではありません。
この第3の相続人のパターン(兄弟姉妹相続事案)の場合、戸籍収集が非常に難しいので、早々に専門家に依頼した方が良いかもしれません。
② 相続人全員の印鑑登録証明書の取得作業
① の戸籍収集作業で相続人が誰であるかが確認できた場合、次に必要なのが相続人全員の印鑑登録証明書の取得作業となります。
相続人全員の印鑑登録証明書(銀行によるが通常、6か月以内に市町村が発行したもの)が必要とされる理由は、いくつかあります。
主な理由としては、相続人様本人の確認(本人確認作業)と、後記③で出てくる署名の記載が、本人の意思に基づくものであることを確認するためです。
銀行の相続は基本的に書面でのやり取りで、相続人に対面するということまではいたしません。
そうすると、銀行が他人ではなく、相続人様が本人の意思で本人が書いたことの証拠として、本人にしか通常取得することのできない印鑑登録証明書及び実印の押印をもとめるのです。
ちなみに、印鑑登録証明書は、原則として、印鑑登録カードをもった方でないと取得できません。
印鑑登録カードは1枚しか発行されませんので、他人が取得することができない仕組みとなっております(例外的に、印鑑登録カードを持参すれば代理人として家族などが印鑑登録証明書は取得できます)。
③ 誰がいくら相続するのか相続人全員が協議をする
銀行の預貯金額がいくらかわかったら遺産分割協議が必要になります。
ここで、単に当該銀行の預金解約のみであれば、全員が銀行の手続き書類に署名押印をすることと受け取る代表者を決めることで足ります。
しかし、当該銀行含め、他の預貯金を合わせて、誰がいくら相続するのか決めないうちに一人の代表の方(代表相続人)が受け取ると後でトラブルになることがあります。
そのため、相続人様全員ですべての遺産についてどう分けるかの協議をする必要があります。
一般的に、相続が発生するとある銀行の預金通帳1通のみという方は少なく、通常は通帳を3冊、世帯主の方が亡くなると不動産も所有しているということもありますので、しっかりと全体の遺産を把握した上で相続人全員が協議をする必要があります。
上記で説明した、第3の相続人のパターンであると、相続人様同士が非常に疎遠、場合によっては会ったこともない方が混ざっているということもありますので、全員での協議が難しい場合も多々あります。
その場合、電話やメール、手紙でのやりとりでも協議したことになりますので、必ずしも一斉に同一場所に集合する必要はありません。
第3の相続人のパターン(兄弟姉妹相続事案)の場合、進め方が非常に難しく初動を間違うと決裂する可能性が高くなるので、相続に詳しい専門家にまずはご相談をするとよいでしょう。
④ 銀行の手続き書類に全員の署名押印、もしくは、遺産分割協議書を用いての相続手続
1つの銀行のみ預金解約を単純にしたいだけの場合、前記①②③の作業をし、それぞれの銀行が用意している相続手続き書類(相続届)に全員が署名、実印での押印をし、受け取る相続人代表者を指定すれば、銀行の解約はできます。
ただし、遺産全体の分け方を決めてから手続きをしないと相続人様の間で後にトラブルとなる可能性があります。
そのため、正式な遺産分割協議書(遺産分割証明書)を作成するのが良いでしょう。
遺産分割協議書は、銀行や信用金庫、不動産登記手続きで利用できるように慎重に作成する必要があります。
遺産分割協議書については、「遺産分割協議書の書き方」で解説しておりますのでよろしければご参考にしてみてください。
専門家に相続手続きを依頼するメリットとは
 相続に詳しい専門家に依頼するメリットは、一言でいうと円満にスピーディーに解決できる可能性が高くなるというところであると思います。
相続に詳しい専門家に依頼するメリットは、一言でいうと円満にスピーディーに解決できる可能性が高くなるというところであると思います。
行政書士は、相続法務の専門家でもありますので、正確性も担保されます。
相続手続きは、相続人様自身が自力でやることももちろん可能ですが、これまで解説してきた通り普段経験のしたことのない作業を多く行う必要があります。
相続手続きは、時間と労力、専門的な知識が要求されます。
相続の実務経験が豊富な専門家に相続手続きの代行を頼むと、初回のご相談時点から見通しが立ち、スピーディーに正確に相続手続きが進みます。
ただし、相続の専門家といっても知識や経験は様々で特長も異なりますのでホームページなどで実績を確認すると良いでしょう。
参考記事
北海道の相続手続きの難しさ
- 1. 普段仲の良かった家族の間でもお金の分配の話になると、北海道にお住いの方同士でも一向に進まない場合もあります。
- 2. 相続人様同士が遠方に住んでいる場合もなかなか話し合いができないこともあります。
例えば、亡くなった方は、函館市に住んでいて、長男は、東京都、長女は、札幌市に住んでいるということもよくあります。大都会に行くと金銭的価値観も変わってくることがありますので、慎重な進め方が必要となります。 - 3. 地方都市であると札幌市と異なり、そもそも銀行の支店窓口がないこともあります。
例えば、三菱UFJ銀行の支店窓口は、札幌市にしかないので、函館などで三菱UFJ銀行の通帳をお持ちの方がお亡くなりになると、札幌市の窓口などに相談に行く必要があります(ただし、郵送や電話でももちろん対応はしてくれます)。 - 4. 銀行の預貯金の他に、山林や原野あるいは畑なども所有している方も多くいます。
売れないような山林や原野あるいは畑を所有している方については、預貯金の相続と合わせて誰が山林や原野あるいは畑を相続するか決める必要があります。
札幌市に事務所のあるたまき行政書士事務所では、相続と遺言の専門事務所で、北海道全域の相続全般のご相談、相続手続きのご依頼をお受けしております。
相続のご相談や相続手続は、手続自体の煩雑さ、多くの時間がかかる以外にも、相続人様の感情問題、民法や税法、保険など多くの知識が要求されます。
たまき行政書士事務所では、相続に詳しい行政書士が直接お客様のご自宅に訪問し、相続全般のご相談をすることができます。
平日夜間や土日も訪問相談を行っております
 たまき行政書士事務所では、忙しいお客様のためにお仕事後の平日夜間相談も行っております。
たまき行政書士事務所では、忙しいお客様のためにお仕事後の平日夜間相談も行っております。
また、平日にご予約いただけましたら、土日のご相談もお受けしております。
先約がなければ、当日や翌日の訪問も可能です。できるだけ早いタイミングで訪問いたします。
まずは、お気軽にお電話、メール又はラインにてお問い合わせください。
銀行別の相続手続き
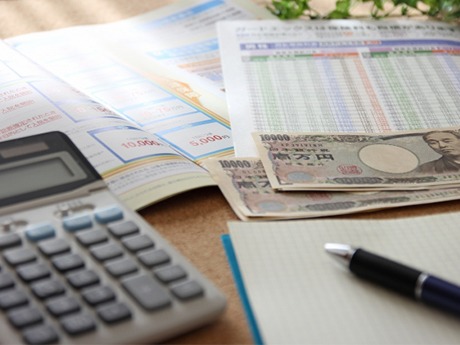 北海道の各銀行・信用金庫の相続手続きについて解説しましたので、ぜひご参考にしていただければと思います。
北海道の各銀行・信用金庫の相続手続きについて解説しましたので、ぜひご参考にしていただければと思います。
一覧にない銀行につきましてもアドバイス差し上げることができますので、分からないことがありましたらぜひ無料訪問相談をご利用ください。
- 北海道信用金庫(旧札幌信用金庫、旧北海信用金庫、旧小樽信用金庫)の相続手続き
- 北海道銀行の相続手続き
- 北洋銀行(旧北海道拓殖銀行・旧札幌銀行)の相続手続き
- 空知信用金庫の相続手続き
- 渡島信用金庫の相続手続き
- ゆうちょ銀行の相続手続き
- 旭川信用金庫(旧富良野信用金庫)の相続手続き
- 北見信用金庫(旧紋別信用金庫)の相続手続き
- 帯広信用金庫の相続手続き
- 遠軽信用金庫の相続手続き
- 北央信用組合(旧千歳信用組合・旧共同信用組合・旧旭川商工信用組合・旧室蘭商工信用組合)の相続手続き
- 稚内信用金庫の相続手続き
- 室蘭信用金庫の相続手続き
- 道南うみ街信用金庫(旧江差信用金庫、旧函館信用金庫)の相続手続き
- 苫小牧信用金庫の相続手続き
- 伊達信用金庫(旧室蘭商工信用組合)の相続手続き
- 釧路信用金庫の相続手続き
- 空知商工信用組合(旧道央信用金庫)の相続手続き
- 釧路信用組合(旧網走信用組合)の相続手続き
- 札幌中央信用組合の相続手続き
- 大地みらい信用金庫(旧根室信用金庫・旧厚岸信用金庫)の相続手続き
- 北空知信用金庫の相続手続き
- 北星信用金庫(旧名寄信用金庫・旧士別信用金庫)の相続手続き
- 北門信用金庫の相続手続き
- 十勝信用組合の相続手続き
- 函館商工信用組合の相続手続き
- みずほ銀行の相続手続き
- りそな銀行の相続手続き
- 三井住友銀行の相続手続き
- 三菱UFJ銀行(旧三菱東京UFJ銀行、旧東京三菱銀行等)の相続手続き
- 農業協同組合(農協、JAバンク)の相続手続き
- 北陸銀行の相続手続き
- 楽天銀行(旧イーバンク)の相続手続き
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。







