前妻との間に子どもがいる夫の相続に備えて、後妻の私がすべきことはありますか?
相続のよくあるご質問札幌 相続トップ>相続のよくあるご質問>前妻との間に子どもがいる夫の相続に備えて、後妻の私がすべきことはありますか?
夫の相続発生の際に、遺産の手続きに困らないように、公正証書遺言を作成していただくのが最適なやり方といえるでしょう。
それでは、前妻との間に子供がいる場合の相続について相続の専門家が解説します。
相続や遺言全般についてお困りの方は、相続・遺言専門のたまき行政書士事務所へお気軽にご相談ください。たまき行政書士事務所では、開業以来多数の公正証書遺言作成のサポートをしております。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEでお問合せください。
LINEビデオやZOOM、Skypeを利用したテレビ電話相続相談も実施しております。
前妻との間に子がいる場合の具体例2つ
【具体例1】夫と後妻との間にも子供がいる場合
【具体例2】夫と後妻との間には子供がいない場合
前妻との間の子がいる場合、難解案件になる理由
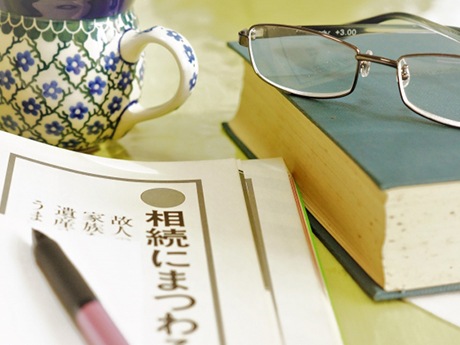 遺言がない場合で、相続手続きを行う場合、相続人全員の合意による遺産分割協議が必要となります。具体例1でいうと後妻と、前妻との間の子と、後妻との間の子の3人が相続人となり、具体例2のように後妻と夫との間の子がいない場合には、前妻との間の子と後妻の2人が相続人となり、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。
遺言がない場合で、相続手続きを行う場合、相続人全員の合意による遺産分割協議が必要となります。具体例1でいうと後妻と、前妻との間の子と、後妻との間の子の3人が相続人となり、具体例2のように後妻と夫との間の子がいない場合には、前妻との間の子と後妻の2人が相続人となり、相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。
後妻と前妻との間の子というのは、葬儀の際以外に、面会したことがないというのが通常です。基本的に、前妻との間の子は、夫とたまに連絡を取っているが、後妻家族とは一切接点がないということがほとんどです。
当然、葬儀の場ですから遺産の分割の話などその場ではでないですが、前妻との間の子でも相続人の一人ということは、前妻との間の子や後妻家族も承知しているため、後日連絡を取り合わなければならないということは互いにわかっております。
そして、その相続手続きが難解案件になる理由は、前妻との間の子が後妻や後妻との間の子に対してあまりよくない印象を持ちやすいということです。
さらに、前妻が再婚をしていない場合には、前妻との間の子は、母が女手一つで子育てをし、苦労しているのを知っているため、実の父と、その後結婚した後妻や、後妻との間の子に対してもっと感情的に割り切れない気持ちになります。
「なぜ、ちゃんと母(前妻)とのときも離婚なんかせずに子育てをしてくれなかったのか」という感情が起きることが通常といえます。
また、前妻についても、離婚しているくらいですので、前夫には良い印象がないことがほとんどです。
以上のことから、遺言を作成していない場合、後妻(現在の妻)としては、どのように後妻との間の子に相続の話のアプローチをしてよいのかわからず、アプローチの仕方を間違うと遺産分割協議が不成立となり、資産が凍結したままとなります。
このような結末がわかっている以上、夫としては生前に対策をすべきといえます。
公正証書遺言を作成し、遺産を確実に移動できるようにする
後妻や後妻との間の子あるいは、前妻との間の子にもいやな思いをさせないために、離婚歴のある夫は、公正証書遺言を作成し、確実に自分の死後、遺産を凍結させたままにならないようにするべきといえます。
具体的には、遺言執行者を後妻とし、財産の行方を指定します。例えば、自宅不動産は、妻に、預貯金は、法定相続分を基準に分けるように指定するということです。または、生前に十分な金銭的サポートを前妻との間の子にしていたのならば、後妻や後妻との間の子がすべて取得するように指定するというのも一つの方法といえます。
いずれにせよ、離婚歴+前妻との間の子供がいる男性(夫)は、公正証書遺言を作成し、ご自身の死後、財産が凍結したままになるのを防ぐ必要があるでしょう。
生前贈与という方法もあるが税金面で高額になる
 年齢がある程度高くなった後、後妻に生前贈与をして遺産分割の際に困らないようにしようと考える夫もいます。この考え方の方が一般的かもしれません。
年齢がある程度高くなった後、後妻に生前贈与をして遺産分割の際に困らないようにしようと考える夫もいます。この考え方の方が一般的かもしれません。
しかし、生前贈与という形となりますので、例えば、不動産でいえば、登録免許税という国税が相続の際の5倍かかり、金銭でも、原則として1年間(1月1日から12月31日までの期間)で110万円を超える金銭の移動には、贈与税がかかり、また、翌年の確定申告の手間や費用がかかります。
確かに、相続の際も相続税という税金がかかることがありますが、相続税の基礎控除額(相続人が2人の場合4200万円)というものがあり、多くの方は、相続税の申告の対象とはなりません。
生前贈与は手間とリスクがあるため、基本的にはあまりお勧めできないことが多いです。
相続と生前贈与の際の税金(登録免許税)の具体例
| 方法 | 登録免許税 | 具体例 (自宅土地建物が2000万円の評価の場合) |
|---|---|---|
| 相続 | 固定資産税評価額の 4/1000 | 8万円 |
| 生前贈与 | 固定資産税評価額の 20/1000 | 40万円 (ただし、減税の例外もあり) |
相続の場合は、固定資産税評価額の4/1000が登録免許税
自宅土地建物が2000万円の評価の場合、相続発生後に名義変更すると8万円が登録免許税
生前贈与の場合は、固定資産税評価額の20/1000が登録免許税
自宅土地建物が2000万円の評価額の場合、40万円が登録免許税(ただし、減税の例外もあり)
公正証書遺言は専門家のサポートを受けて作成することが多い
公正証書遺言は、公証人が遺言者の口述を書き留めて作成したという形式をとりますが、遺言を作成しようとする方が直接公証役場に出向き、不動産などの根拠資料を自分で集め、さらに、自身の生活状況などを踏まえ時間をかけて公証人と1対1で進めるということは難しいこともあります。
そのため、多くの場合、公正証書遺言を作成する際には、行政書士や弁護士などの法律の専門家と遺言者が時間を十分にかけて打ち合わせ、遺言内容を決め、行政書士や弁護士などの士業者が遺言の原案を作成し、不動産や預貯金の根拠資料なども士業者が集め、公証役場に持参し、公正証書遺言完成という流れを取ります。具体的には、
- 1. 行政書士など士業者と打ち合わせ
- 2. 行政書士など士業者が不動産の資料や預貯金の資料などを収集
- 3. 打ち合わせの際の遺言者のお気持ちや遺言者の指定した財産の行方を法律文書にして遺言原案を行政書士等の士業者が作成
- 4. 行政書士等の士業者が最寄りの公証役場に出向き、遺言原案を基に公証人と打ち合わせて、日程を調整
- 5. 公証役場にて、公正証書遺言正本完成(当日の所要時間は30分程度)
となります。
遺言を公正証書遺言にする理由
 前妻との間に子がいる方の遺言は、一般論として偏った遺言内容(後妻家族側の取り分が多くなる)になりがちのため、遺言を否定される可能性が比較的高いといえます。
前妻との間に子がいる方の遺言は、一般論として偏った遺言内容(後妻家族側の取り分が多くなる)になりがちのため、遺言を否定される可能性が比較的高いといえます。
自筆証書遺言は、本人の直筆で書きますが、遺言者自身が密室で書くことも多いため、本人の筆跡かどうか筆跡鑑定でもしない限り確認できません。また誰かに強制されて書かされた遺言となれば無効の主張の要因となるために、作成過程が厳密な公正証書遺言とした方が良いです。
公正証書遺言は、利害関係者が遺言作成の現場に立ち会うことができず、公証人以外に、利害関係のない立ち会い証人が2人必要となるため、公正証書遺言の効力を否定されるケースが非常に少ないといえます。
また、手続的にも自筆証書遺言のような検認作業が必要ないですし、実務を行う印象だと、銀行や法務局での遺言の信用性は公正証書遺言の方が高いです。
そのため、特に前妻との間の子がいる男性の遺言については、手続的に厳格で、遺言の効力が否定されにくい、かつ、実務的に相続手続きがスムーズに進む公正証書遺言にするのがよいでしょう。
たまき行政書士事務所では、遺言と相続の専門事務所として開業以来多数の公正証書遺言作成のサポートをしております。札幌市内、札幌圏、北海道内での遺言をご検討の方は、ご自宅まで無料で訪問いたしますので、お気軽にご相談、お問合せください。
遺言を作成することなく夫の死亡が発生したときは
 ここまで、離婚歴があり、前妻との間に子供がいる男性の相続は、難解案件となることが多いと解説しましたが、遺言を作成することなく男性が死亡してしまった場合には、相続の専門家を一人でも間に入れると相続手続きがスムーズにいくことが期待できます。
ここまで、離婚歴があり、前妻との間に子供がいる男性の相続は、難解案件となることが多いと解説しましたが、遺言を作成することなく男性が死亡してしまった場合には、相続の専門家を一人でも間に入れると相続手続きがスムーズにいくことが期待できます。
前妻との間の子がいる相続事案では、感情問題に配慮しながら、遺産を隠すことなく開示し、最良のタイミングで案内を出す必要があります。
この最良のタイミングと案内文の書き方などは、長年の経験値がものをいいます。単に法律家というだけではなく、相続専門の法律家である必要があります。
札幌市北区に事務所があるたまき行政書士事務所は、相続遺言の専門事務所として開業以来長年、前妻との間に子がいる方の相続を多数経験しております。
- どのように進めてよいかわからない
- 葬儀の際前妻との間の子とあったがそれっきり連絡を取れないでいる
という後妻側のご家族様は一度札幌市北区で相続遺言が専門のたまき行政書士事務所にご相談ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。










