令和4年4月1日から満18歳で成年へ変更になったことによる相続分野への影響について
相続・遺言コラム令和4年4月1日から成年となる年齢が20歳から18歳へ変更となりました
 長年議論されていた成年となる年齢の引き下げが実行され、令和4年4月1日から、成年となる年齢は満20歳から満18歳へ変更となりました。
長年議論されていた成年となる年齢の引き下げが実行され、令和4年4月1日から、成年となる年齢は満20歳から満18歳へ変更となりました。
そのため、令和4年4日1日時点で、満18歳を迎えている方や満19歳の方は、すでに成年となりました。
私人間(しじんかん)の契約に関する法律は、民法という法律を中心に定められており、民法で成年となる年齢を満18歳と定めたことで、喫煙、競馬や競輪などのいわゆる公益ギャンブルなどを除き、ほぼすべての行為(契約など)が満18歳から親の同意なくできるようになりました。
ちなみに、喫煙や公益ギャンブルができる年齢が引き下げられなかった理由は、私見ですが、わざわざ引き下げる道理がない上に、健康や精神にも良くないため、国民の理解が得られにくいと国が考えたものと思われます。
いままでも親の同意があれば契約自体はできた
 いままでも法定代理人である親の同意があれば、未成年でも契約自体はできたのですが、実務では、法定代理人の真の同意があることを証明するのが煩わしく、後のトラブルを防止するため、携帯電話などの契約は親の名前で契約していたという実情があります。
いままでも法定代理人である親の同意があれば、未成年でも契約自体はできたのですが、実務では、法定代理人の真の同意があることを証明するのが煩わしく、後のトラブルを防止するため、携帯電話などの契約は親の名前で契約していたという実情があります。
今回の成人年齢の引き下げによって、特に恩恵を受けるのは、高校を卒業してすぐに社会人となった方ではないでしょうか。
高校を卒業してすぐに就職してお金を稼ぐ能力があっても、いままでは、親の同意なくアパートの契約をすることも、携帯電話を契約することも基本的にできませんでした。
これでは、一人前の社会人としては認められていないようなものです。
これからは満18歳になるとほぼすべての契約行為、国家資格の取得が可能となる
令和4年4月1日から施行される民法改正(成年年齢引き下げ)によって、高校を卒業してすぐに就職をする方は、アパートの契約、クレジットカードの作成、携帯電話の契約など、様々な契約が自分一人ででき、大変便利となるでしょう。
また、行政書士や司法書士などの資格取得後の登録などもできるようになります。そのため、年齢による参入障壁もなくなり、有能な方が能力を眠らすことなく早くから社会で活躍できるチャンスが増えます。
(欠格事由)
行政書士法
第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二(省略)
制度の大まかな説明は、政府広報のホームページがわかりやすいため、参考に載せておきます。
ちなみに、選挙権については、今回の民法改正(成年年齢引き下げ)に先行して満18歳へ引き下げが行われているため、今回の民法改正の影響は受けません。
なお、「成年」とほぼ同じ意味で「成人」もよく使われていますが、正しくは、成年といいます。そのため、満18歳未満の方については、未成年と呼びます。
(成年)
民法
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
相続、遺言分野への影響
当事務所は相続と遺言の専門事務所ですので、ここでは、成年となる年齢の変更が、相続や遺言の分野にどう影響するのか解説したいと思います。
遺言について
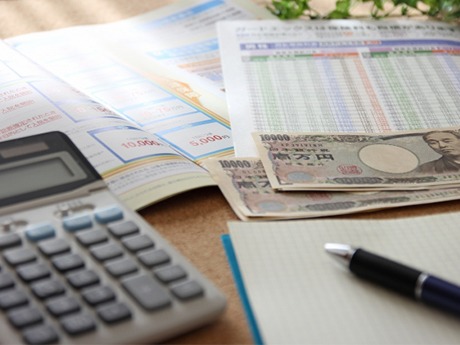 遺言については特別な変更点はありません。遺言は、満15歳から有効となるため、成年となる年齢が満20歳から満18歳に変更されたからといって、特段変更はないと言えるでしょう。
遺言については特別な変更点はありません。遺言は、満15歳から有効となるため、成年となる年齢が満20歳から満18歳に変更されたからといって、特段変更はないと言えるでしょう。
ただし、行政書士などの資格者への公正証書遺言原案の作成の依頼については、契約の一種となりますので、満15歳になったからといって必ずしも、契約当事者になれるわけではありません。
しかし、これからは満18歳になれば確実に依頼者となることができますので、若干の変更はあると言えるかもしれません。
(遺言能力)
民法
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
相続について
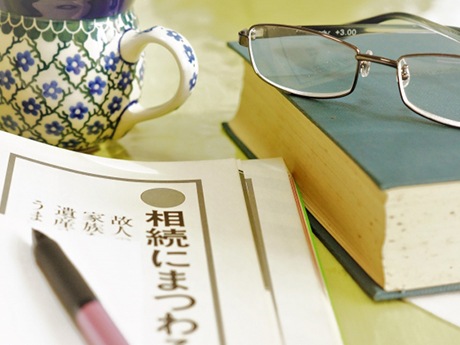 相続分野では、今回の民法改正(成年年齢引き下げ)に伴い大きな変更点が1つ出てきます。
相続分野では、今回の民法改正(成年年齢引き下げ)に伴い大きな変更点が1つ出てきます。
これまでは、満18歳、満19歳の方は遺産分割協議に参加できませんでしたが、令和4年4月1日からは、満18歳、満19歳の方も遺産分割協議に参加できるようになります。
これは、今回の民法改正(成年年齢引き下げ)の大きな改善点といえます。
例えば、亡くなった満50歳の男性A(子供から見ると父)には、満50歳の妻Bと、満20歳の子供Cと、満18歳の子供Dがいるとします。
男性Aの相続手続きの際に、遺産分割協議書や銀行の相続手続き書類に署名押印するとき、これまでの民法の規定では、満18歳の子供Dは未成年扱いとなるため、署名押印することができませんでした。
しかし、令和4年4月1日の民法改正施行日以降には、満18歳の子供Dも遺産分割協議に参加したり、遺産分割協議書への署名押印、相続手続き書類に署名押印できることになります。
令和4年3月31日までは、満18歳の方が遺産分割協議に参加する必要がある場合、家庭裁判所に特別代理人選任申立てという手続きをしなければならず、非常に煩わしい手続きとなっておりました。
煩雑すぎる手続きのため、満18歳の子が満20歳になるまで待ってから手続きをするというご家庭もあるくらいでした。
なぜ、子供Dの法定代理人である妻B(母親)が代わりに署名押印できないのか簡単に説明すると、外形上、妻Bと子供Dは利益相反の関係になり、妻Bが子供Dを代理するのは適当ではないという民法の考え方によります。
まとめ
 今回は、時事ネタとして令和4年4月1日施行の民法改正(成年年齢引き下げ)についてコラムを書きましたが、実際に相続にお困りの際には、一度、相続に詳しい専門家に個別具体的に相談するのが良いと思われます。
今回は、時事ネタとして令和4年4月1日施行の民法改正(成年年齢引き下げ)についてコラムを書きましたが、実際に相続にお困りの際には、一度、相続に詳しい専門家に個別具体的に相談するのが良いと思われます。
最近では、相続の無料相談をする事務所が増えております。お気軽に一度ご相談をしてみるのが良いでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








