遺言か養子縁組か
相続・遺言コラムよくある事例
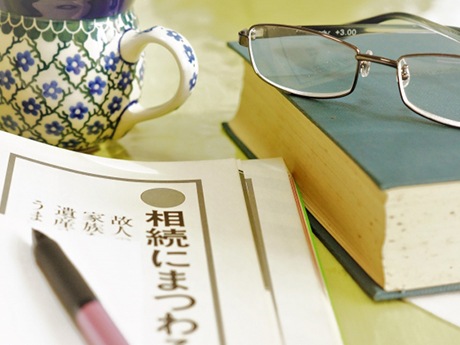 現在の夫婦の間に子供はいないのだが、妻側の(前夫との間の)連れ子がいる場合、何も対策をしなければ、夫の不動産や預貯金を妻の連れ子へ残すことができません。
現在の夫婦の間に子供はいないのだが、妻側の(前夫との間の)連れ子がいる場合、何も対策をしなければ、夫の不動産や預貯金を妻の連れ子へ残すことができません。
夫の不動産や預貯金を妻の連れ子に渡すには、養子縁組か遺言を作成することによって妻の連れ子に相続(遺贈)させる必要があります。
問題はそのどちらが適切であるかです。
養子縁組をしたときに起こること
妻側の連れ子が15歳未満でまだ小さいときには、次に、夫となる方と連れ子を養子縁組(妻が代諾縁組をする)をすることが実の父のようになるという意味で効果的かもしれません。
養子縁組をすることでいわゆる養父の“嫡出子”の身分となり、法律上も実の子と同様に育てることができます。
(嫡出子の身分の取得)
民法
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
次に、連れ子の方がすでに成人しており、扶養することはもう特になくなっているが、将来の相続発生のために妻の連れ子に財産を渡そうとする場合、養子縁組または遺言を検討することになります。
結論からすると、連れ子が成人しているような場合には、養子縁組ではなく、遺言、特に公正証書遺言を作成することの方がよいと思います。
ケースバイケースではありますが、養子縁組をすると基本的に苗字を養親の姓に変えなくてはならず、養子となる方(妻の連れ子)に負担がかかるからです。
(養子の氏)
民法
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
また、養親と養子のみでなく養親の親族の相続が発生した場合にも、相続人となってくる場合があるので、相続のためだけに養子縁組をするというのは必要以上の対策となってしまうかもしれません。
遺言を作成する際は公正証書遺言の方がよい
 養子縁組ではなく、遺言を作成することによって連れ子に財産を残せるようにしようと決めた場合、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成した方が良いです。
養子縁組ではなく、遺言を作成することによって連れ子に財産を残せるようにしようと決めた場合、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成した方が良いです。
自筆証書遺言は、実務では不備の多いものが多く、せっかく作っても利用できない場合があります。
公正証書遺言にしておくとそのような不備はほぼ生じ得ないですので、遺言を作成するなら公正証書遺言がおすすめです。
今回は、一般例として解説しましたが、どのようにすべきかは個別具体的に検証する必要がありますので、迷った場合には、お近くの相続や遺言の専門家にご相談するとよいでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








