自筆証書遺言の落とし穴
相続・遺言コラム自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
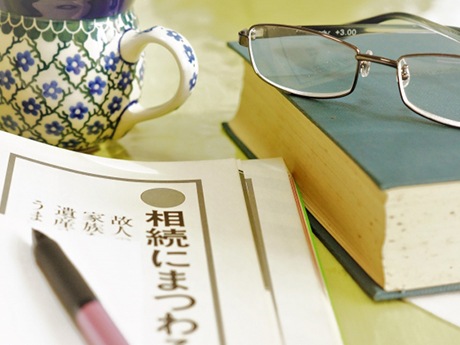 自筆証書遺言は、自分の筆跡で誰の立ち合いもいらず、無料で遺言が作成できるもので、要件も緩やかです。そのため、要件が厳格で費用が掛かる公正証書遺言よりも、自筆証書遺言を作る方が多いかもしれません。
自筆証書遺言は、自分の筆跡で誰の立ち合いもいらず、無料で遺言が作成できるもので、要件も緩やかです。そのため、要件が厳格で費用が掛かる公正証書遺言よりも、自筆証書遺言を作る方が多いかもしれません。
最近、書店には、自筆証書遺言の作成本なども売り出されており、また、最近の民法改正で自筆証書遺言の保管方法が創設されたため、今は自筆証書遺言ブームと言ってもよいかもしれません。
しかし、遺言・相続を多く扱う実務家としては、自筆証書遺言による死亡後のトラブルを何例も見てきていることから、遺言の形式の中で、自筆証書遺言を選択するのは、危険性が高いと言えます。
たまき行政書士事務所では、せっかく遺言を書いても、その後紛争が起きてしまってはいけないという観点から、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
今回は、実際に遭遇した例を参考に、自筆証書遺言の落とし穴をかなり具体的に紹介していきたいと思います。
自分だけで自筆証書遺言を作成した例、あるいは他の事務所(行政書士事務所、司法書士事務所、弁護士事務所)で自筆証書遺言を作成した例で、その自筆証書遺言を利用する段階で当事務所が相談を受けた例です。
自筆証書遺言の落とし穴①~遺言執行者の記載が無かった事例
 自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
検認が終了すると、証明書に家庭裁判所の書記官の認証印が押され、自筆証書遺言にホチキス留めで添付されます。このような検認の過程を経て初めて、自筆証書遺言を各種手続きで使えるようになります。
通常、遺言の記載内容を実現するために、遺言の中で、遺言執行者(遺言内容を実現する業務を果たす人)が指定されますが、この事例では遺言執行者の記載がありませんでした。
遺言執行者の記載がないとどうなるか
遺言執行者の記載がない場合、金融機関(銀行、信用組合など)では、「相続人全員で遺言執行者を指定してください。相続人の一人であるAさんを指定するのであれば、遺言執行者をAさんとすることの同意書を相続人全員からもらってきてください」と言われます。
しかし、遺言というのは相続人全員に平等に分配するという内容となっているケースはほぼなく、誰か1人に相続させるという偏った内容であることがほとんどなので、遺言によって不利益を受ける相続人がその遺言執行者の同意書にサインするはずがなく、結局、同意書の添付ができないので、金融機関の相続手続はできず、自筆証書遺言は、“絵にかいた餅”の状態となります。
遺言執行者の記載のない自筆証書遺言は、自筆証書遺言の形式を満たしていたとしても、銀行など金融機関の実務では使えない遺言といえます。
トラブルを避けるための対策
公正証書遺言を作成するのがベストですが、金銭的な事情等により自筆証書遺言を作成する場合には、必ず、“遺言執行者の指定をする”ということが大切です。
誰を遺言執行者とするかについては、その自筆証書遺言によって利益を受ける方=受遺者が適任でしょう。
受遺者であれば、その自筆証書遺言を実現する動機にもなり、高い確率で遺言が執行されることになるでしょう。
ただし、事前にその遺言執行者に、
- ⅰ. 自筆証書遺言の保管場所を教えておく
- ⅱ. 遺言執行者に指定しておいたと伝達する
ことが大切です。
自筆証書遺言の落とし穴②~自筆証書遺言無効の裁判や無効確認の調停を提起された事例
紀州のドンファン事件
 わかりやすい事例として、テレビのワイドショーで話題となった、“資産家・紀州のドンファンの遺言事件”が挙げられます。
わかりやすい事例として、テレビのワイドショーで話題となった、“資産家・紀州のドンファンの遺言事件”が挙げられます。
自筆証書遺言は、遺言を残す方が手書きで書き、多くの場合一人で書くため、筆跡が違う他人が書いたものではないか(偽造した遺言である)、あるいは誰かに無理やり書かされたものではないかといった理由で、無効であると異議を申し立てられることが多々あります。
紀州のドンファン事件は、「いごん(遺言の意味)」というタイトルの書面が出てきて、“個人の財産のすべてを(和歌山県)田辺市にキフ(寄付)する”という内容が書かれていたのですが、その遺言は不自然である、本人が書いていないとして遺言者の兄らが遺言無効の主張をした事件です。
紀州のドンファン(野崎幸助さん)は、死亡日時点で妻はいましたが子供がいないので、遺言が無効になれば、紀州のドンファンの兄弟姉妹が相続人となり、遺言者の兄らには遺言の無効を主張するメリットがあります。
利害関係者から遺言の無効の確認の裁判(地方裁判所)や遺言の無効の調停を提起されるリスクあり
遺言がないと、相続人が対等な立場で遺産分割協議ができるのに対し、遺言があると、通常はかなり偏った遺産分割がされるので、遺言によって不利益を受ける相続人からすると、自筆証書遺言が出てくると、無効であると主張したくなります。
自筆証書遺言は、形式としては簡単に有効になるのですが、実質判断としては、有効と認めてもらうにはかなりの要件を満たす必要があります。形式が有効になることを前提として、遺言を書いた時に、
- ⅰ. 遺言を作成する能力があったこと
- ⅱ. 本人が書いたということ
- ⅲ. 本人の意思で書いたということ(強要などされていない)ということ
- ⅳ. 内容に合理性があること
を満たす必要があります。
紀州のドンファンなどの資産家でなくとも、自筆証書遺言の事例では、日常的に無効確認主張がなされていて、結論として無効とはなるケースは少なくとも、遺言受遺者に金銭的、精神的負担がかかります。
金融機関が、遺言の無効確認の裁判や調停が行われていることを知ると、解決するまでは相続手続きに応じてくれません。後で、金融機関が紛争に巻き込まれるリスクがあるからです。
ご高齢者や認知症がある方の自筆証書遺言はリスクあり
ご高齢の方で字があまり書けなくなっていて、認知症があるという場合、
- そもそもこの時期は字が書けなかったはずだし、書けたとしても認知症であったから、このような自筆証書遺言は、受遺者Aさんが無理やり書かせたに違いない
- 受遺者となっているAさんが遺言者の筆跡を真似して書いたものだ
と言われて、自筆証書遺言の無効を主張されるリスクがあります。
トラブルを避けるための対策
高齢者の自筆証書遺言は、無効を主張されるリスクがあります。無効の主張理由として意外と多いのが、内容が不自然である(合理性がない)という理由です。
“Aさんにすべての財産を相続させる”と書いていたが、“私(Bさん)も生前、遺言者からとても可愛がられていた。そのためAさんにすべての財産を相続させるという遺言は不自然であり、本人の意思で書いているとは思えないので無効である”
というものです。
このようなトラブルを避けるためには、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成するべきです。
公正証書遺言は、
- ① 遺言を残したい人の口述を公証人が聞き取って書いた
- ② 利害関係のない証人二人の面前で作成した
- ③ 公証人が本人確認作業をしてから作成した
という体裁をとっているので、内容が具体的で、無効になることはまずありません。
公証人は、元裁判官、元検察官、元弁護士など法律家の中でもとても優秀な方で、準公務員なので、間違いは起こりえないという信頼もあります。
高齢者の方、認知症が多少ある方の遺言は、公正証書遺言を作成する方が確実です。
なお、認知症=遺言が作成できないというわけではありません。
遺言能力は、認知症判定とは別個のもので、遺言の内容を理解し、遺言を作成したいという意思があれば広く認められるものです。
遺言能力の最終判断は、公正証書遺言では公証人が行います。
自筆証書遺言の落とし穴③~内容が不明確、あるいは内容を特定できないとして、銀行など金融機関で遺言を利用した手続ができなかった事例
 自筆証書遺言は、検認では形式が広く有効となります。形式が有効となれば、一応、実務でも遺言ありの手続の土俵に上がることになります。
自筆証書遺言は、検認では形式が広く有効となります。形式が有効となれば、一応、実務でも遺言ありの手続の土俵に上がることになります。
ただし、自筆証書遺言の内容の有効性を判断するのは、法務局の登記官や金融機関の最終判断者ですので、手続き段階で自筆証書遺言が否定されることもあります。
否定される理由として一番多いと思われるのは、遺言に書かれている内容が不明確、不特定というものです。
内容が不明確、不特定の事例
(事例1)内容が不明確
例えば、
下記金融機関の預貯金口座のすべてをAさんに相続させる。
〇〇銀行 □□支店 口座番号 0123456
と書かれていたとします。
もし、口座番号が本当は0123457だとしたら、この自筆証書遺言の内容で手続きして良いのかどうか不明確です。不明確な遺言を手続きして良いものかどうか判断するのは、金融機関の最終判断者となります。
最終判断者が、内容が不明確なので応じられないと判断した場合、手続きはできないこととなります。
(事例2)内容が不特定
私の財産を、友人の佐藤大介にすべて遺贈する。遺言執行者を佐藤大介に指定する。
という自筆証書遺言が出てきたとします。
「佐藤大介」さんは比較的よくある名前なので、多くの方があてはまることもあり、人物を正確に特定できない場合があります。佐藤大介さんが遺言執行者として手続きに行っても、指定された佐藤大介さんだと特定できないことを理由に対応してもらえない可能性があります。
不明確、不特定とならないための方法
内容を明確にする方法は、具体的に書くことです。ただし、具体的に書けば書くほど誤字や脱字が出やすく、内容が不明確になるという矛盾も生じます。
それを避けるためには、具体的に書きつつ、具体的な内容から外れたものも含まれるようにすると良いでしょう。
例えば、
以下を含む預貯金及び現金等金融資産のすべてをAに相続させる。
〇〇銀行 □□支店 口座番号 0123456
という書き方です。
こうすることで、口座番号の誤字などがあっても、Aさんに相続させるということが明確になるので、金融機関に遺言内容を否定されるリスクは少なくなるでしょう。
また、人物の不特定については、例えば、佐藤大介さんの生年月日や、遺言を書いた時点での佐藤大介さんの住所を記載するとよいでしょう。
しかし、一番良い方法は、やはり公正証書遺言にすることです。
公正証書遺言の作成などについてご相談ください
 公正証書遺言を作成する場合、自分で公証役場の公証人のところに相談に行くよりも、行政書士など遺言に詳しい専門家に相談して、原案を作ってもらってから作成するということが実務では多く行われています。
公正証書遺言を作成する場合、自分で公証役場の公証人のところに相談に行くよりも、行政書士など遺言に詳しい専門家に相談して、原案を作ってもらってから作成するということが実務では多く行われています。
行政書士に依頼することで、必要な戸籍や証明書などの資料収集を任せることができ、遺言を作成したいと思った背景についても、時間をかけてゆっくりと相談できます。
ただし、遺言や相続の実務に日頃から携わっている方に相談するのが必須です。
遺言と相続手続きは表裏一体で、どちらの実務の経験も積んでいないと遺言作成の正しいアドバイスはできません。
たまき行政書士事務所では、公正証書遺言のご相談を行っております。まずは、お気軽にお電話、メール、ラインにてお問い合わせください。
北海道内であれば、交通費も無料で訪問相談を行っております。
ご自宅、施設でのご相談、夜間、土日のご相談も可能です
公正証書遺言を作成しようという方は、ご高齢の方も多く、移動が困難の方も多いです。たまき行政書士事務所では、行政書士が、ご自宅や入居施設まで訪問してご相談に応じております。
平日夜間や土日の訪問相談も、事前にご予約いただけましたら対応しております。
テレビ会議相談も行っております
 令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
令和2年3月以降、新型コロナウィルスの影響で面会でのご相談もしばらく控えたいというお客様もいらっしゃると思います。
対面でのご相談よりもテレビ会議でのご相談を希望される方については、テレビ会議相続相談(オンライン相続相談、リモート相続相談)が可能です。
テレビ会議相続相談は、出張訪問相続相談と同品質で時間をかけて行っております。
事前にご予約を行っていただければ、初回1時間相続や遺言のご相談を無料でお受けしております。
無料テレビ会議相続相談のあとそのままご依頼をしたいとご希望のお客様については、そのままスムーズにご契約を行うことも可能です。
テレビ会議ですので、インターネット環境が整っていれば、北海道の離島(利尻島など)の方や東京都、神奈川県の方など遠方の方もご相談可能です。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








