住所が分からない相続人がいる場合の遺産分割協議や相続手続について
相続・遺言コラム疎遠な相続人がいる場合に起こること
 いわゆる兄弟姉妹相続事案で特に多いのですが、法定相続人(以下、「相続人」)の1人もしくは数人が疎遠で、現在の住所が分からないということがよくあります。
いわゆる兄弟姉妹相続事案で特に多いのですが、法定相続人(以下、「相続人」)の1人もしくは数人が疎遠で、現在の住所が分からないということがよくあります。
相続人の住所が判明せず、コンタクトが取れない方が一人でもいる場合は、基本的に遺産分割協議や相続手続きはできないことになっています。
そのため、遺産分割協議や相続手続きをするには、疎遠な相続人の方の正確な現住所を、何らかの手段で判明させる必要があります。
遺産分割協議や相続手続きには、原則として相続人全員の署名と、実印および印鑑登録証明書が必要です。
参考記事
住所が分からない相続人がいる場合の対処法
住所がわからない相続人がいる場合の対処法を紹介します。
戸籍の附票で住所を判明させる
相続手続きに必要な戸籍を集める過程で、相続人の戸籍の附票を一緒に請求します。戸籍の附票は、簡単に解説すると戸籍に紐づいている住所録です。
事務所では、「相続人の一人が疎遠で住所などが全くわからないのですが、大丈夫ですか」とのご相談をよく受けますが、戸籍の附票によって、疎遠な相続人の現住所が9割近い確率で判明します。
参考記事
戸籍の附票を取得すると職権消除と記載されている場合
行方不明の場合
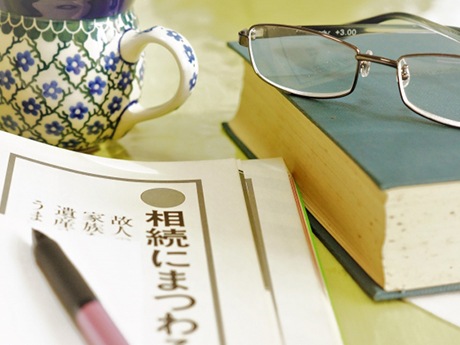 戸籍の附票を取得できても、職権消除されている(住所録が消去されている)場合があります。これは、実際は死亡している可能性が高いけれども、死亡届が出ていないために、戸籍上は生存していることになっていたからだと考えられます。
戸籍の附票を取得できても、職権消除されている(住所録が消去されている)場合があります。これは、実際は死亡している可能性が高いけれども、死亡届が出ていないために、戸籍上は生存していることになっていたからだと考えられます。
例えば、一人暮らしの方が自宅以外で死亡したり、行方不明になると、親族や近隣の方が役所に死亡届を提出することができないので、戸籍の附票や住民票だけが消去(職権消除)されます。
この場合、相続人が利害関係人として失踪宣告の申立てをして、法律上死亡させる(戸籍を除籍にさせる)ということをする必要があります。
法律上とはいえ人を死亡させる行為であるので、相続人も家庭裁判所も、失踪宣告の手続は慎重に行うべきであることは言うまでもないですが、通常、戸籍を見れば死亡しているだろうということは読み取れます。
失踪宣告の手続きは時間がかかりますが、申立て自体はそれほど複雑なものではないため、相続人の方自身でも手続きできる場合が多いでしょう。
失踪宣告の申立てを専門家に代わってもらう場合は、裁判所への手続きなので、司法書士の方や弁護士の方に依頼する必要があります。
参考HP
超高齢である場合
120歳以上の超高齢の場合に職権消除できる制度もあります。120歳以上の場合にのみ利用できる制度ですので、相続人が120歳以上生きていることになっている場合、高齢者職権消除をしてもらうように依頼し、戸籍に死亡の記載をしてもらいます。
参考記事
相続人が第三者に住所を開示しない措置をとっている場合
 配偶者や親からのDV被害を防止する、あるいはストーカーに住所を判明されないようにするといった理由で、相続人の方が、戸籍の附票や住民票を第三者に取得できないようにする措置をとっている場合があります。
配偶者や親からのDV被害を防止する、あるいはストーカーに住所を判明されないようにするといった理由で、相続人の方が、戸籍の附票や住民票を第三者に取得できないようにする措置をとっている場合があります。
このDV等支援措置の申し出がなされている場合、相続人、あるいは相続人から依頼を受けた行政書士、司法書士、弁護士などが戸籍の附票を請求しても、自治体の方は戸籍の附票を出してはくれません。
基本的に、相続人の方の住所が判明できないとわかったその時点で、遺産分割協議や相続手続きはかなり難しくなります。
費用対効果を考慮すると、住所が判明できない場合には、遺産分割協議や相続手続きはあきらめた方が良い場合もあります。
最終手段として不在者財産管理人を選任する
相続財産が少額であれば、遺産分割協議や相続手続きをあきらめるのも一つの手段です。
しかし、故人が固定資産税の発生している不動産を所有している場合や、故人に多額の預貯金がある場合には、家庭裁判所を利用した複雑な手続きとなりますが、不在者財産管理人を選任して遺産分割協議や、相続手続きを行うという方法もあります。
不在者財産管理人を選任する手続きは、一般の方が自力で行うにはかなり難しいと思いますので、司法書士の方や弁護士の方に一度ご相談するとよいでしょう。費用や時間がかかるので、不在者財産管理人の制度を利用するのは、かなり限られた場合といえるでしょう。
参考HP
相続人がいなくても相続手続きができる場合がある(遺産分割協議は不可)
 あくまで例外的なやり方ですが、銀行の相続手続きには、ⅰ. 簡易相続手続きという方法があります。簡易相続手続きは、一般的には、100万円以下(銀行により基準は異なる)の普通預金の相続手続きのことをいいます。
あくまで例外的なやり方ですが、銀行の相続手続きには、ⅰ. 簡易相続手続きという方法があります。簡易相続手続きは、一般的には、100万円以下(銀行により基準は異なる)の普通預金の相続手続きのことをいいます。
相続人の一人が相続人であることを示して、その相続人が全責任を負った上で銀行に誓約書を提出し、凍結された預貯金の全額を受け取るというものです。
もう一つの方法として、ⅱ. 預貯金の仮払い制度を利用した相続手続きもあります。預貯金の仮払い制度は、簡単にいうと、銀行ごとに口座残高の3分の1の額に対し法定相続分(法定相続割合)のみ請求できるというものです。
預貯金の仮払い制度については、別の記事で詳しく解説しておりますので、よろしければご参照ください。
まとめ
 今回は、疎遠な相続人の現住所がわからない場合の遺産分割協議や相続手続きについて、網羅的に解説しましたが、ほとんどの場合、相続人の方の住所は戸籍の附票で判明しますので、まずは相続手続きに必要な戸籍を収集すると良いでしょう。
今回は、疎遠な相続人の現住所がわからない場合の遺産分割協議や相続手続きについて、網羅的に解説しましたが、ほとんどの場合、相続人の方の住所は戸籍の附票で判明しますので、まずは相続手続きに必要な戸籍を収集すると良いでしょう。
ただし、疎遠な相続人が出てくるケースの多くは、いわゆる兄弟姉妹相続の事案ですので、戸籍収集自体がかなり大変ですので、初期の段階で相続の専門家に相談すると良いでしょう。
たまき行政書士事務所は相続と遺言を専門としており、複雑な相続手続きを解決した実績がたくさんあります。
近くの専門家に相談したけれども解決できなかった、表面的な相談のみで深い相談ができなかったという方は、一度北海道札幌市に事務所のある、相続遺言専門・たまき行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








