札幌市の住民票オンライン申請について
相続・遺言コラム相続手続きや公正証書遺言の作成時に不可欠な住民票
 相続手続きや公正証書遺言を作成するときなどには、住民票を使います。
相続手続きや公正証書遺言を作成するときなどには、住民票を使います。
日常的な手続きでは、本人確認資料に運転免許証や保険証を利用することもありますが、銀行などの相続手続きや不動産の相続手続き、あるいは公正証書遺言の作成時の本人確認には住民票を提出する必要があります。
住民票には、正式に住民登録している住所が正確に記載されております。
そのため、相続手続きや遺言作成時に法律・法務の職業の方が作成する書面には、基本的に住民票の住所を記載します。
札幌市での住民票の請求方法(令和3年10月時点)
札幌市内に住民登録をしている方が、自分の住民票を請求する方法をご紹介します。
- 1. 住民登録している区役所の窓口に出向いて請求する(札幌市北区民であれば、札幌市北区役所に出向く)
- 2. 札幌市内の区役所で行きやすい窓口に出向いて請求する(住民登録していない区役所でも可)
例えば、札幌市北区民であっても、札幌市西区役所の方が行きやすいのであれば、札幌市西区役所で請求する。
※ 札幌市の区役所では、窓口に出向いた場合は特別に他の区の住民票も発行してくれます。札幌市の制度はとても親切です。 - 3. 大通証明サービスコーナー(地下鉄大通駅近く、地下1階)の窓口に出向いて請求する
- 4. 住民登録している区役所に郵送で請求する
※ 例えば、札幌市北区民であれば、インターネットで「札幌市 北区 住民票 郵送請求」と検索すると、札幌市北区役所に住民票を郵送請求する方法(郵送等による証明請求/札幌市)が出てきます。
具体的には、上記でプリントアウトした住民票の請求書、運転免許証のコピー、定額小為替350円分(1部請求の場合)、返信用封筒(84円切手を貼っておく)を封筒に入れて、住民登録している区に送る。
※ 事前にゆうちょ銀行で定額小為替を購入しておく必要があります(詳しくは「戸籍請求の際に使うゆうちょ銀行の定額小為替について」をご参照下さい)。 - 5. コンビニの複合機でマイナンバーカードを利用して請求する
- 6. スマートフォンやPCでオンライン申請(請求)をする(令和3年10月新設)
★ 上記5と6の方法では、マイナンバーカード(通知カードでは不可)が必要となります。
以上のように、札幌市では住民票を取得する手段が6つもあります。今回のコラムでは、6番目の請求方法である住民票のオンライン申請(請求)の方法について解説します。
住民票のオンライン申請(オンラインでの請求+自宅で受け取り)の概要
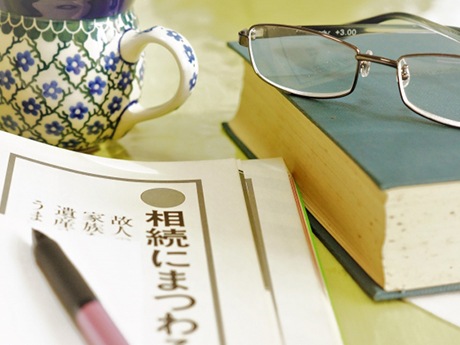 コロナ禍になってから、Amazonや楽天などのネットショッピングを利用する方が多くなりましたが、役所の手続きなども同じように、区役所の窓口やコンビニなどに行かずに自宅で完結したいという方も多いのではないでしょうか。
コロナ禍になってから、Amazonや楽天などのネットショッピングを利用する方が多くなりましたが、役所の手続きなども同じように、区役所の窓口やコンビニなどに行かずに自宅で完結したいという方も多いのではないでしょうか。
自治体側も、多くの方が来所し密になるよりは、オンラインで請求してくれた方がいいと考えていますし、業務の効率化も図れます。
そこで、札幌市では、スマートフォンやPCを利用して住民票(住民票以外にもオンライン申請できる証明書は今後増えると予想されます)を請求する仕組みを整えました。
早速、当事務所でも実験的に住民票オンライン申請をやってみましたが、スマートフォンのみで行うのが一番簡単であると思います。
札幌市のホームページの説明ではわかりにくいという方もいるかと思いますが、マイナンバーを利用して確定申告を電子申告したことがある方や、日常的にネットショッピングをしている方であれば、おそらく5分もあればオンライン申請(請求)が完了しますので非常に便利です。
次の章で、オンライン申請の手順を簡単に解説してみましたので、よろしければご参考にしてみてください。
住民票のオンライン申請(請求)の方法(スマートフォンのみで行う場合)
事前に、スマートフォンでGrafferIdentity(グラファーアイデンティティー)というアプリをダウンロードする。
「札幌市 住民票 スマート請求」と検索し、札幌市のホームページの該当ページに進む。
ページの下の方にある住民票のオンライン申請(請求)はこちら(外部サイトへ)に進む。
「ログインして申請に進む」というボタンを押す。
アカウント登録(グラファーアカウントを登録する)をする。GoogleアカウントまたはLINEアカウントでもログインできます。
利用規約に同意するに✓を入れ、「申請に進む」というボタンを押す。
氏名(カタカナ)、郵便番号、電話番号の3点を入力し、「一時保存して次へ」というボタンを押す。
区役所窓口で請求する際にも聞かれる5つの質問にチェックを入れる。
- ⅰ. 世帯全員か、世帯一部か
- ⅱ. 世帯主氏名と続柄を記載するか、しないか
- ⅲ. 本籍筆頭者を記載するか、しないか
- ⅳ. 変更事項(備考欄)を記載するか、しないか
の区別にチェックを入れ、
- ⅴ. 必要な通数
を入力し、もう一度「一時保存して次へ」というボタンを押す。
※ 相続や遺言で住民票を利用する際は、本籍筆頭者と続柄は記載した方が良いです。
申請者の情報(簡略版)が出てくる。
ページの下の方にある「個人認証する」というボタンを押す。
署名用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード発行時にご自身で設定した英数字6文字以上の番号)を入力する。
マイナンバーカードをスマートフォンにかざし、ICチップの情報を読み取る。
読み取りに成功したらクレジットカード情報を入力し、料金が表示されたら「次へ進む」というボタンを押す。
申請内容を確認し、間違いがなければ「この内容で申請する」というボタンを押す。
申請完了を知らせるメールが届く。
住民票のオンライン申請(請求)を試した感想
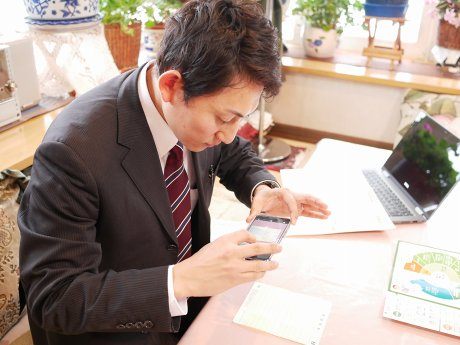 一見大変そうですが、スマートフォン操作に慣れている方であれば、5分位で申請が完了します。郵送請求だと、1通の住民票を請求するのに早い方でも15分はかかるので、時間短縮にもなり便利といえるでしょう。
一見大変そうですが、スマートフォン操作に慣れている方であれば、5分位で申請が完了します。郵送請求だと、1通の住民票を請求するのに早い方でも15分はかかるので、時間短縮にもなり便利といえるでしょう。
オンライン申請と郵送請求の料金(総額)を比較すると、住民票を1通請求するのに、オンライン請求が総額434円(住民票代350円+切手代84円=434円)なのに対し、郵送請求は、切手代が請求時の分と返信用封筒の分が必要ですし、定額小為替の発行手数料もかかるので、総額618円(住民票代350円+切手代84円×2、定額小為替発行手数料100円)かかります。オンライン申請の方が費用も安くなります。
たまき行政書士事務所では、スマートフォンのみでの方法と、PCとスマートフォンを組み合わせる方法の両方を試しましたが、アプリの特性上、スマートフォンのみで行う方がマイナンバーカードの読み取りが圧倒的にスムーズでしたので、現状、たまき行政書士事務所では、スマートフォンのみで行うオンライン申請をおすすめします。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








