札幌市の市街化調整区域の相続について
相続・遺言コラムはじめに
 相続が発生すると自宅の土地建物や預貯金あるいは証券などの資産が、遺産分割協議を経て、現在生きている相続人に移転されます。
相続が発生すると自宅の土地建物や預貯金あるいは証券などの資産が、遺産分割協議を経て、現在生きている相続人に移転されます。
その際、あまり一般の方には活用ができない(売却も容易にできそうにない)市街化調整区域の土地も被相続人の相続財産として存在する場合があります。
- 市街化調整区域の土地はいらないし、どこにあるかわからないけど権利証が出てきて困っている
- 名義変更せずそのままにしておいてよいのか
- 相続するとしたらだれが相続するのか
- 相続した後処分できるのか
という相談をお受けすることが当事務所では頻繁にあります。
また、2025年に突如、噴出した南区の体験型動物園ノースサファリの問題もテレビのニュースなどで取り上げられ市街化調整区域に関心がある方も増えてきております。
そのため、今回の相続コラムでは、市街化調整区域全般についてと市街化調整区域の土地の相続について札幌市の事情を踏まえて解説いたします。
市街化調整区域と市街化区域の違い
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域という意味です。
これとは、反対に市街化区域とは、住居や店舗などの建築物が並ぶようにインフラも整備し、市街地の開発を積極的にすでに進めている地域、あるいは、これから10年以内に開発を進める予定のある地域のことをいいます。
市街化区域は、開発を進めるために水道・電気・ガスなどのインフラが整っており、用途地域により制限がありますが、建築物も建てることができますので、住宅利用や店舗利用、工場利用や自動車整備場などに活用されます。札幌市内の不動産業者が主に仲介しているのは、この市街化区域の不動産です。市街化区域の不動産を相続した場合、人口が多い札幌市内の場合、買い手を見つけることが容易にでき、何ら苦労なく売却ができるでしょう。不動産屋さんに依頼すると概ね3か月位で売れることが予想されます。
市街化調整区域は、私の経験則ですが9割以上の不動産仲介会社は仲介物件として扱うことはありません。不動産業の間では、単に‘‘調整区域’’と呼び、調整区域ということが判明した時点で「当店では、調整区域のため取り扱っていません」といわれることが多いと思います。不動産仲介業者としては、市街化調整区域は、仲介手数料が見込めず、境界線も不明瞭であることがほぼすべてなので、扱うメリットよりデメリットの方が大きいため、よほどの常連の方以外は、市街化調整区域の仲介はお断りすると思います。
市街化調整区域の特徴
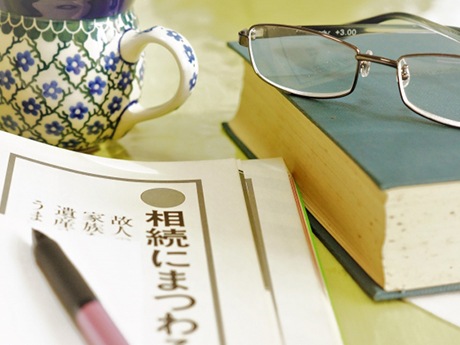 市街化調整区域は、建築物を原則建てることが出来ないため、市場価値としては、非常に低いものとなります。札幌市でいうと条や丁目が付いていないところ札幌市北区○○町〇番〇というところが市街化調整区域と考えればよいでしょう。
市街化調整区域は、建築物を原則建てることが出来ないため、市場価値としては、非常に低いものとなります。札幌市でいうと条や丁目が付いていないところ札幌市北区○○町〇番〇というところが市街化調整区域と考えればよいでしょう。
正確に調べるには、札幌市の札幌市地図情報サービスで調べるとよいでしょう。市街化区域か市街化調整区域かがわかります。色がついていれば、市街化区域、色がついていないグレーの地域が市街化調整区域です。
参考(札幌市HP)
市街化調整区域は、原則として(農家の自宅や倉庫以外の)建物が建てられないというのが特徴なのですが、札幌市では結構数多くの市街化調整区域に建物が建っているのが現状です。
これには様々な理由が考えられますが、一つは取り締りが札幌市は甘いこと(マンパワーが足りないのかもしれません)、もう一つは、建物や建築物の定義があいまいということで、これが最大の原因と思われます。
建物は、土地に定着して壁があるもののことをいいますが、建築物は、これより概念が広く壁がない柱や屋根のあるものも含みます。例えば、車庫は、建物、カーポートは建築物となり、車庫は、固定資産税がかかり、カーポートは固定資産税がかかりません。
そのため、少し余談になりますが、札幌市の住宅では、自動車への積雪を防ぐことができ、固定資産税がかからないカーポートの設置が人気です。市街化調整区域でいう建築物は、都市計画法上の建築物(建築基準法上の建築物と同定義)を指すため、建築物にあたるカーポートも建てられないという結論となるでしょう。
太陽光発電などは、建築物といえますが、例外的に建築が可能というものもあるため詳しく知りたい方は、札幌市の都市計画課に聞くと正確な情報が得られるでしょう。
(建物)
不動産登記規則(下線や太字は、たまき行政書士事務所にて追記)
第百十一条 建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
(用語の定義)
建築基準法(下線や太字は、たまき行政書士事務所にて追記)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
第二項(省略)
(定義)
都市計画法
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
10 この法律において「建築物」とは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号に定める建築をいう。


話を戻しますが、市街化調整区域に建築物が多くなってしまったのは定義にあいまいな部分が残るからだと思います。土地に定着するというのが建築物としての要件なのですが、土地に定着するというのがどのような場合定着なのかがはっきりしないからです。
そのため、例えば、コンクリートブロックの上に設置している物置は土地に定着しているといえるのか、同じくコンクリートブロックの上に乗っかっているユニットハウス(いわゆる‘‘スーパーハウス’’)は定着しているといえるのか(ユニットハウスにくっついているのは、単にコンクリートブロックではないか)など議論が成り立つわけです。
土地に定着するという意味の定義は、法律上明確ではないですが、判例では、民法86条1項の定着物は、継続的に土地に固着し、しかも固着して使用されることが、その物の取引上の性質とみられるものとされています(大判昭10.10.1)。参考(札幌市市街化調整区域の解)
今後の予想
 ノースサファリのニュース以降、市民の声もあり、今後、札幌市では市街化調整区域について調査が行われることが予想されます。マンパワーの問題もあり、全部の取り締まりはできないことが予想されます。
ノースサファリのニュース以降、市民の声もあり、今後、札幌市では市街化調整区域について調査が行われることが予想されます。マンパワーの問題もあり、全部の取り締まりはできないことが予想されます。
そして、市街化調整区域でご商売をしたい方は、車両として扱われるトレーラーハウスを活用することが考えられます。タイヤがパンクしていないすぐに動かすことのできるトレーラーハウスであれば、土地に定着している建築物とは言われないと思います。
市街化調整区域の相続と売却について
このような議論があり、市街化調整区域については、まだ需要が流動的な部分がありますが、市街化調整区域の特性を知ったうえでの売買であれば、売却処分ができる可能性があります。
市街化調整区域の土地をお持ちの方が亡くなった場合には、まずは、相続登記をして、売却ができる準備をするとよいでしょう。
たまき行政書士事務所では、市街化調整区域の売却は、原野売却個人間売買サポートというサービスを行っておりますのでどうしても処分したいという方は札幌市、石狩市限定となりますがご相談ください。
市街化調整区域は、ほとんどの場合(免税点以下のため)固定資産税がかかっておりませんので、相続してそのまま持ち続けるというのも選択肢の一つといえるでしょう。
無料訪問相談・無料テレビ電話相談のご予約や、ご質問等はお気軽に
たまき行政書士事務所の無料訪問相談について >>
【新型コロナ対策】LINEビデオ、ZOOM、Skypeでの無料テレビ電話相談も可能 ≫
道内でも札幌から遠方の方(稚内市や根室市、北見市、函館市)はZOOM等リモート面会だと、即日ご相談が可能です。北海道外の本州からもZOOMでの相続相談を積極的に行っております。難しい相続事案などで近くの事務所で断られた案件など、相続専門のたまき行政書士事務所にお気軽にご相談ください。他の事務所で解決できなかった事案でも、解決できることが多々あります。

たまき行政書士事務所の
ごあんないABOUT
相続・遺言専門のたまき行政書士事務所
- 代表 行政書士 田巻裕康
-
[住所]
北海道札幌市北区北32条西5丁目3-28
SAKURA-N32 1F
011-214-0467
070-4308-1398(行政書士直通電話)
電話受付:平日9時~18時 - [交通アクセス]
地下鉄南北線:北34条駅(3番出口)から徒歩1分
相続遺言YouTube教室 随時更新中!
行政書士田巻裕康による相続・遺言に関する解説動画をYouTubeにて公開中。一般のお客様はもちろん、相続実務を行ったことのない行政書士の方もぜひご活用ください。








